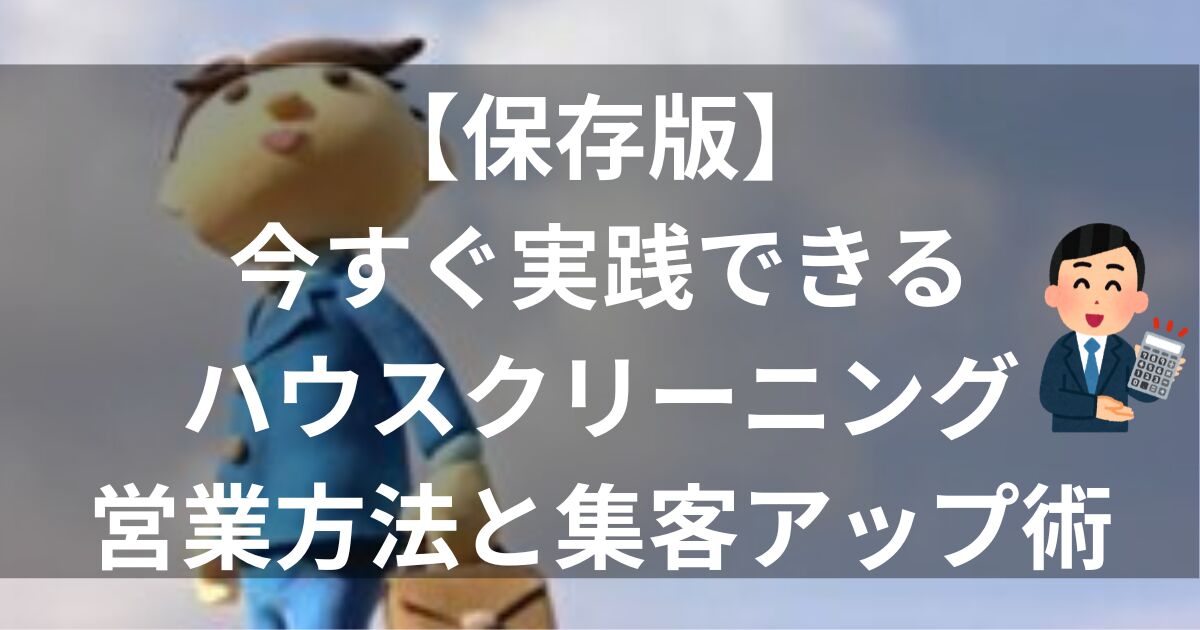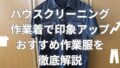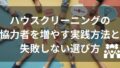-
お客様をどうやって増やせばいいのか分からない
-
飛び込みや電話営業がとにかく苦手だ
- リピーターや紹介につなげるにはどうしたらいいの?
-
チラシ・ホームページ・SNSの作り方が分からないよ

このような悩みや疑問にお答えします
この記事では、実際に大手清掃会社出身の筆者が、個人でも成果を出せる具体的な営業方法をわかりやすく解説します。
現場で培った実践的なノウハウをもとに、「チラシ」「ホームページ」「マッチングサイト」「飛び込み営業」など、初心者でもすぐに取り組める戦略を中心にまとめました。
営業が苦手だと感じている方や、これから個人で清掃業を始めようとしている方にも役立つよう、各手法の効果を高めるコツ、そして実際の成功事例まで紹介します。
本記事を読むことで、限られた時間と予算の中でも成果を出すための考え方と行動パターンが明確になります。
ぜひ、日々の営業活動に取り入れてみてください。
【この記事を読んでわかること】
- 反応を生むチラシ設計と配布戦略を習得できる
- 検索に強いホームページとローカルSEOの要点を理解できる
- マッチングサイトやSNSで新規獲得を加速する手順を把握できる
- 初回対応からフォローまでの定期化フローを実践できる
ハウスクリーニングで新規顧客を獲得する4つの方法
チラシで効果的に集客するポイント
チラシは、地域密着型のハウスクリーニング営業において、最も費用対効果の高い広告手法の一つです。
特に、個人事業主や小規模経営者にとっては、大規模な広告費をかけずに地元での認知を広げることができるため、開業初期の段階で非常に有効な集客手段といえます。
まず効果を最大化するためには、「誰に伝えるのか」を明確にすることが何よりも重要です。
たとえば、子育て世帯なら「掃除する時間が取れない」、高齢者世帯なら「高所の掃除が難しい」、共働き世帯なら「平日の時間がない」など、それぞれの悩みや生活背景に合わせた訴求を設計する必要があります。
チラシの内容をターゲット別に最適化することで、読んだ人の共感を得やすくなり、反応率が高まります。
次に、デザインのポイントです。
清潔感と信頼感を重視した配色を心がけましょう。
一般的に、青や白を基調とした色は清潔で誠実な印象を与えます。また、ビフォーアフターの写真や作業中の様子を掲載すると、視覚的にサービスの品質を訴えることができます。
フォントは丸みのあるゴシック体やメイリオなど、読みやすく温かみのある書体を選ぶとよいでしょう。
さらに、チラシの中には「行動を促す仕掛け」を必ず入れることが大切です。
例えば、「今だけ初回30%OFF」や「LINE予約で500円引き」など、具体的な特典を提示することで、問い合わせまでの心理的ハードルを下げることができます。
また、「期間限定」「先着○名様」といった言葉を添えると、行動を後押しする効果が高まります。
配布方法にも工夫が必要です。ポスティングだけに頼るのではなく、複数の経路を組み合わせて露出を高めましょう。
以下のような方法が効果的です。
- 地域のスーパーや商業施設の掲示板に設置する
- 地域のイベントやマルシェなどで手渡しする
- 既存顧客からの紹介を促す「紹介カード」として利用する
-
不動産会社やリフォーム業者に設置を依頼する
このように接点を増やすことで、単発の反響ではなく継続的な集客基盤を築くことができます。
また、配布する地域の選定は感覚に頼らず、客観的なデータを活用するとより精度が上がります。
たとえば、総務省統計局が公開している「国勢調査」では、地域ごとの年齢層や世帯構成を確認することができます(出典:総務省統計局「国勢調査」 )
この情報をもとに、子育て世帯や高齢者が多いエリアを優先して配布することで、より効率的に反応を得ることができます。
最後に、チラシ配布後の効果測定を行うことが大切です。
クーポンコードやQRコードを印刷しておけば、どのエリア・デザイン・キャンペーンが反応を得たかを数値で分析できます。
これにより、次回配布時にはより成果の出る内容に改善でき、広告コストを最小限に抑えることが可能です。
このように、ターゲット設定・デザイン・配布戦略・効果測定を一体化して行うことで、チラシは単なる紙の広告から、「利益を生み出す戦略的営業ツール」へと進化します。
配布エリアとタイミングを戦略的に決める
チラシ配布の成果は、内容やデザインよりも「どこで・いつ配るか」によって大きく左右されます。
効果的なエリア選定と配布時期の最適化を行うことで、同じ枚数でも反応率が2倍以上に上がることも珍しくありません。
単に「たくさん配る」ではなく、「反応が見込める層に届ける」という考え方が重要です。
まずは、エリア選定の考え方から整理してみましょう。
ハウスクリーニングの主なターゲットは、以下のような属性に分類されます。
- ファミリー層が多い住宅街:共働きで掃除の時間が取れない家庭が多く、定期清掃や水回りクリーニングのニーズが高い。
- 築年数が10年以上経過した地域:キッチン・浴室・エアコンなどに汚れやカビが蓄積しているため、クリーニング依頼率が高い傾向にあります。
-
高齢者の多いエリア:身体的に掃除が負担になりやすく、継続的な利用に繋がりやすい。
これらの条件を満たす地域を見つけるには、自治体の統計資料やオープンデータを活用するのが効果的です。
たとえば、総務省統計局が提供している「都道府県・市区町村のすがた(社会・人口統計体系)」では、市区町村単位で年齢別人口構成や世帯構造を確認することができます(出典:総務省統計局)
このような客観的データを活用すると、感覚に頼らない戦略的なエリア設定が可能です。
次に、配布タイミングの最適化です。
清掃業は季節や生活行動の変化と密接に関係しており、「需要が自然に高まる時期」に合わせて広告を打つことで、より高い効果が得られます。代表的な繁忙期とその特徴を挙げると以下の通りです。
| 時期 | 主な需要要因 | 配布に適したタイミング |
|---|---|---|
| 12月〜1月 | 年末の大掃除需要 | 11月中旬〜12月上旬 |
| 3月〜4月 | 引っ越し・新生活準備 | 2月下旬〜3月中旬 |
| 6月〜7月 | 梅雨時のカビ・エアコンクリーニング | 5月下旬〜6月上旬 |
| 9月〜10月 | 台風・湿気対策、秋の清掃 | 8月下旬〜9月上旬 |
このように、需要の1か月前に配布を行うのが基本です。
人々が掃除を意識し始めるタイミングにチラシが届くと、「ちょうどお願いしたいと思っていた」と感じてもらいやすくなります。
加えて、曜日や時間帯も無視できません。
平日よりも土日の午前中にポスティングされたチラシは、家庭でゆっくり確認される確率が高いとされています。
特に土曜午前は反応率が高い傾向にあり、地域によっては平日夜よりも約1.5倍の問い合わせが発生することがあります。
配布後は、成果を数値で検証することが不可欠です。
チラシにQRコードを設置して自社サイトやLINE公式アカウントに誘導したり、「チラシ限定クーポンコード」を発行して利用件数を測定したりすることで、どのエリアやデザインが最も効果的だったかを分析できます。
データを蓄積すれば、次回配布時には「反応率の高いエリア×最適な時期」という勝ちパターンを確立でき、少ないコストで安定した集客が可能になります。
このように、ハウスクリーニングのチラシ配布は「感覚」ではなく「データと時期」に基づく戦略設計が成果を決めます。
的確なエリアとタイミングを見極めることこそ、地域で信頼される清掃サービスへの第一歩です。
ホームページで信頼を高めるSEO対策

ホームページは、ハウスクリーニング事業における「24時間営業の名刺」であり、「信頼を生み出す営業マン」でもあります。
現代では、チラシや口コミで関心を持ったお客様が、まず最初に行うのが“検索”です。
つまり、どれほど技術力が高くても、検索結果に表示されなければ新規顧客に出会う機会を失ってしまいます。
そのため、SEO(検索エンジン最適化)を意識したホームページ設計は、顧客獲得の要といえるのです。
まず意識すべきは、「検索されやすいキーワードの設定」です。
Googleなどの検索エンジンは、ユーザーが入力する検索語(クエリ)とサイト内の情報を照合して、関連性の高いページを上位表示します。
たとえば「ハウスクリーニング ○○市」「エアコンクリーニング 料金」「水回り清掃 おすすめ」など、地域名+サービス名の組み合わせは非常に効果的です。
地域を限定したキーワードは競合が少なく、個人事業主でも上位表示を狙いやすいのが特徴です。
次に重要なのが、タイトルタグ(title)と見出し(h1〜h3)への適切なキーワード配置です。
Google公式ガイドラインによれば、検索エンジンはページタイトルや見出しの文言を重視してコンテンツの主題を判断します(出典:Google 検索セントラル「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」 )
そのため、「○○市のハウスクリーニングなら〇〇クリーンサービス|エアコン・水回り対応」といった形で、主要キーワードを自然に盛り込みながら、ユーザーにとって分かりやすいタイトルを設定することが推奨されます。

ポイントはね、タイトルや見出しに“狙いたいキーワード”を自然に入れることなんだよ!検索エンジンにもユーザーにも、ページの内容がパッと伝わるようにするのがコツだね。
さらに、コンテンツの充実度がSEOの鍵を握ります。
単なるサービス紹介にとどまらず、「よくある質問」「掃除のコツ」「作業の流れ」「料金の根拠」など、ユーザーが知りたい情報を体系的に掲載することで滞在時間が伸び、検索評価が高まります。
特にハウスクリーニング業は「信頼性」が重視される分野のため、作業前後の写真やお客様の声の掲載が非常に効果的です。
写真にはオリジナル性があり、実際の仕事ぶりを可視化することで「この業者なら安心して任せられる」という心理的な信頼を得られます。
レビューやお客様の感想を掲載する際は、実際の感想を簡潔に紹介し、誇張表現を避けることが重要です。
また、SEOと並行して取り組みたいのが、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)への登録です。
登録することで、Google検索やGoogleマップ上に事業情報が表示され、地域ユーザーからのアクセスが増加します。
営業時間、サービスエリア、写真、口コミへの返信などを定期的に更新することで、検索結果の上位に「地図付き店舗情報」として表示される可能性が高まります。
実際に、ローカルSEO(地域検索対策)を行っている企業は、していない企業に比べて平均1.7倍のクリック率を獲得していると報告されています。
さらに技術面では、スマートフォン対応(モバイルフレンドリー)が必須です。
Googleのモバイルファーストインデックスにより、検索順位は主にスマホ版ページを基準に決定されるため、スマホで見やすいデザインにすることが評価向上に直結します。
文字サイズ、ボタンの押しやすさ、読み込み速度などを定期的にチェックし、改善していきましょう。
最後に、サイトの更新頻度と透明性も信頼を左右します。
「施工実績を毎月更新」「キャンペーン情報を定期投稿」「ブログで掃除ノウハウを発信」など、情報発信を継続することで、Googleから“活動的な事業者”と認識され、評価が安定して上がります。
また、料金や対応エリアを明確に表示し、追加費用の有無を正直に記載することで、顧客からの信頼度が飛躍的に高まります。
このように、SEO対策とは単なる「キーワードの設定」ではなく、「検索され、見られ、信頼される仕組みづくり」です。
ホームページをただの情報掲載の場ではなく、“信頼構築と集客の両方を担う営業資産”として活用すれば、24時間体制で新しい顧客との出会いを生み出すことができます。
SNS・口コミを活用してファンを増やす

現代のハウスクリーニング業において、SNSは単なる情報発信の場ではなく、「信頼を育てるプラットフォーム」として欠かせない存在になっています。
特に、個人事業主や地域密着型の清掃業者にとっては、広告費をかけずに自分の仕事ぶりを直接お客様に伝えられる最も効果的なツールの一つです。
適切に運用すれば、SNSは口コミを生み出し、リピーターや紹介顧客の獲得に繋がります。
まず取り組みやすいのが Instagram(インスタグラム) です。
視覚的な情報発信に優れており、「掃除のビフォーアフター」「作業中の様子」「使用している洗剤や道具の紹介」などを写真や動画で投稿することで、清掃のプロフェッショナルとしての技術をわかりやすく伝えることができます。
特に、ハッシュタグ(例:「#ハウスクリーニング」「#エアコンクリーニング○○市」)を活用すると、地域ユーザーの目に届きやすくなります。

調査によれば、83%の回答者が Instagram で商品・サービスを見て何らかの行動を起こしたと答えています。
また、LINE公式アカウント は、既存顧客との関係を深める上で非常に効果的です。
登録してくれた顧客に、定期的にお得なキャンペーン情報や清掃のワンポイントアドバイスを配信することで、「役に立つ情報をくれる信頼できる業者」という印象を育てられます。
さらに、LINEのチャット機能を使えば、問い合わせから予約までをスムーズに行えるため、顧客体験(CX)を向上させることができます。
公式LINEを導入する際は、リッチメニュー(画面下部のボタン)を設定し、「料金表」「作業メニュー」「口コミページ」などに誘導できるようにしておくと利便性が高まります。
次に、SNS運用で成果を出すためのコツとして 「価値提供型コンテンツ」 を意識しましょう。
単に宣伝するだけではフォロワーは増えません。
「プロが教える掃除のコツ」「季節ごとのお手入れチェックリスト」「知らないと損する汚れ防止法」など、ユーザーが保存・シェアしたくなる実用的な情報を投稿することで、自然とファン層が拡大していきます。
これにより、まだ依頼を検討していない潜在顧客の信頼を先に獲得できるのです。
さらに、SNSと並行して 口コミ対策(レビュー・評価管理) を行うことも重要です。
Googleビジネスプロフィールやくらしのマーケットなどの口コミ欄は、見込み客が最も重視する要素の一つです。
良いレビューはもちろん、万が一低評価があった場合も誠実に返信し、改善姿勢を示すことが信頼構築につながります。
口コミは「評価」ではなく「信頼構築の対話」として捉え、顧客との関係性を深める機会として活用しましょう。
また、SNSを運用する上で注意すべきは、一貫性と継続性 です。
投稿頻度が不規則だったり、デザインやトーンがバラバラだったりすると、プロとしての印象が損なわれます。
投稿スケジュールをあらかじめ決めて、ブランドカラーやロゴ、フォントを統一することで「この投稿はあの業者だ」と認識してもらいやすくなります。
無料のデザインツール(例:Canva)を使えば、テンプレートを活用して誰でも簡単に統一感を持たせた投稿が作成できます。
最後に、SNSは「数」よりも「質」が重要です。
フォロワー数を増やすことよりも、投稿に反応してくれる“関係性の深いファン”を増やすことを目指してください。
そのためには、コメントへの返信、ストーリーズでのアンケート、フォロワー限定のキャンペーンなど、双方向のコミュニケーション を大切にしましょう。
お客様が「この人にお願いしたい」と感じる瞬間は、単なる宣伝ではなく、信頼と共感の積み重ねによって生まれます。
SNSと口コミの力を掛け合わせることで、広告費をかけずに「地域の信頼ブランド」を築くことができます。
ハウスクリーニング業においてファンを育てるとは、単なるフォロワー獲得ではなく、「信頼を積み上げ、紹介が生まれる仕組みを作る」ことなのです。
この投稿をInstagramで見る
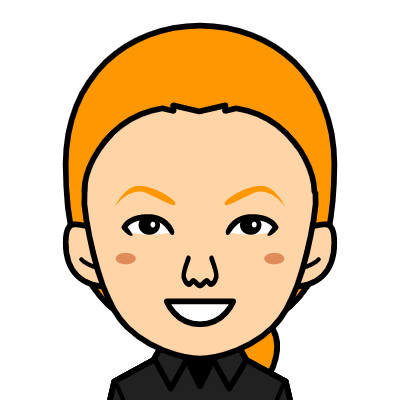
インスタで有名な『キレイのいろは』さんは、私と同じ女やのに、なんでもできるからほんまにすごいわ〜
マッチングサイトを使った効率的な営業
 画像出典:エキテン
画像出典:エキテン ![]()
近年、ハウスクリーニング業界では「マッチングサイト」を活用した営業が急速に広がっています。
これは、顧客がオンライン上で清掃業者を比較・選定し、依頼できるサービスのことで、個人事業主にとっては新規顧客と出会う最短ルートとなっています。
従来のチラシや飛び込み営業に比べ、コストを抑えながら高確度の見込み客と接点を持てるため、効率的かつ継続的に集客が可能です。
代表的なマッチングサイトには、以下のようなプラットフォームがあります。
これらのサイトを最大限に活用するためには、プロフィールページの作り込みが鍵を握ります。
顧客はプロフィールを見て依頼の可否を判断するため、他の事業者と差別化できる情報を丁寧に整備することが重要です。
まず、サービス内容と料金体系を明確に記載しましょう。
曖昧な表現や「お問い合わせください」といった文言は避け、具体的な価格を提示することで信頼性が向上します。
例えば「エアコンクリーニング:1台9,000円(税込)/防カビコート込み」など、分かりやすく整理された情報は顧客に安心感を与えます。
また、「得意分野」を具体的に打ち出すことも効果的です。
「ペット臭の除去」「高所エアコン対応」「女性スタッフ同行可能」など、顧客が自分のニーズに合う業者を選びやすくなります。
次に、実績写真と作業風景を掲載することが信頼獲得の大きなポイントです。
清掃前後の比較写真はもちろん、使用している機材や洗剤の説明を添えることで、技術力と安全性を可視化できます。
さらに、口コミ(レビュー)対策も欠かせません。
マッチングサイトの多くは、レビューの数と評価がランキングや検索順位に影響します。
顧客がサービスに満足した際は、「ぜひレビューを書いていただけると嬉しいです」と一言添えるだけで投稿率が上がります。
また、レビューに対しては良い内容も悪い内容も誠実に返信することが重要です。
ポジティブなコメントには感謝を、ネガティブな内容には改善への意志を丁寧に伝えることで、他の閲覧者にも誠実な印象を与えられます。
さらに、リピート導線の設計も忘れてはいけません。
マッチングサイト経由の一回限りの依頼で終わらせず、作業後のフォロー連絡や定期清掃プランの提案を行うことで、継続的な顧客関係を構築できます。
たとえば「年に一度のエアコン清掃をおすすめしています」など、次回提案を自然に行うことで再依頼の確率が高まります。
最後に、複数サイトへの登録を検討する場合は、料金や条件を統一することが重要です。
サイトごとに異なる価格を設定してしまうと、顧客が不信感を抱く可能性があります。
また、掲載情報を更新しないまま放置すると検索順位が下がるため、月1回程度は情報を見直す運用習慣を持ちましょう。
マッチングサイトは、正しく活用すれば“営業を自動化できる仕組み”になります。
自分から営業をかけるのが苦手な人でも、オンライン上で信頼と実績を積み上げることで、安定した集客を実現できるのです。
飛び込み営業で信頼を築くコツ

ハウスクリーニング業における飛び込み営業は、デジタル集客が主流となった今でも「地域に根ざした信頼関係を構築する最も直接的な手段」として有効です。
確かに心理的なハードルは高いものの、実際に顔を合わせて誠実さを伝えられる点で、オンラインにはない強みがあります。
特に、地域密着型でリピート顧客を増やしたい個人事業主にとって、飛び込み営業は“地元に根を張る第一歩”となる戦略です。
まず、アプローチ先を戦略的に選定することが重要です。
清掃ニーズの高い業種・施設をリストアップし、業務内容にマッチした提案を行うことで、成約率が大幅に向上します。
以下のような業種は特に狙い目です。
-
飲食店(エアコン清掃・グリストラップ清掃・床ワックス)
油汚れや臭いの除去など、衛生管理が厳しく求められる業界のため、定期契約のチャンスが豊富。 -
不動産会社(空室クリーニング・入退去時のハウスクリーニング)
管理物件が多いため、1社との取引で複数物件の案件を受注できる可能性がある。 -
美容室・オフィス・クリニック(床メンテナンス・窓ガラス清掃)
来客型の業態で清潔感を重視するため、長期的な清掃契約につながりやすい。
訪問時は、必ず「名刺」「料金表」「清掃実績を示す写真(Before/After)」の3点セットを携帯しましょう。
特に写真は、言葉以上にサービス品質を伝えられる“無言の営業資料”です。
デジタル端末に数枚保存しておくと、現場でもすぐに提示できて便利です。
料金表は明朗にし、基本料金とオプションの範囲を具体的に記載しておくと信頼度が高まります。
営業トークでは、まず最初の15秒が勝負です。
相手の時間を奪わないよう、「挨拶 → 用件 → メリット提示」を簡潔に伝えましょう。
たとえば、「近くで清掃サービスをしておりまして、定期的な床清掃の無料見積もりをさせていただければと思いまして」など、相手の関心を引きやすい提案から入ると効果的です。
特に、無料見積もりや一部施工のデモンストレーションを提案することで、相手がリスクを感じにくくなり、話を聞いてもらいやすくなります。

私の知っている業者さんは、病院限定で一部の床を無料で剥離ワックスしてから定期契約を取るやり方で、年間50件も契約を取ったみたいですよ。
また、営業において最も重要なのは「その場での成約」よりも「後日のフォロー」です。
訪問時に名刺を置いて帰るだけでも、後日問い合わせにつながるケースは少なくありません。訪問後には、電話やメール、もしくはLINE公式アカウントなどでお礼と再提案を行いましょう。
このようなフォローアップの継続性が、他社との差別化要因になります。
中小企業庁の調査でも、「顧客は初回提案から5回目以降の接触で契約に至る割合が最も高い」という結果が示されており、粘り強いアプローチが成約率を左右することがわかります。

あーそれって2:8(ニッパチ)5:8(ゴッパチ)の法則だね。

なんじゃー、それ!ニッパチゴパッチて、いったいなんのことなんね!

さらに、飛び込み営業では「相手にとって価値のある情報提供」を意識することが成功の鍵です。
単なるサービスの売り込みではなく、「床のワックスの剥離は3年に一度行うと美観を保てます」や「換気扇の油汚れは放置するとモーターの寿命が縮まります」など、プロとしての知識を活かしたアドバイスを添えると、専門家としての信頼が生まれます。
この“教育的営業”は、すぐに契約につながらなくても、後日「やっぱりお願いしたい」と思い出してもらえる可能性を高めます。
また、飛び込み営業を効率化するためには、訪問エリアと時間帯の最適化も重要です。
たとえば、飲食店はランチ前後の忙しい時間を避け、午後2時〜4時頃が比較的対応してもらいやすい傾向にあります。
オフィスビルなどは週の前半(火〜水曜)に訪問すると担当者が在席している可能性が高いです。
このように、業態別の生活リズムを理解し、訪問タイミングを調整することで、無駄足を大幅に減らせます。
最後に、飛び込み営業を通して得た情報は必ず記録・分析しましょう。
訪問先、担当者名、反応内容、次回フォロー予定日などをリスト化し、CRM(顧客管理ツール)やスプレッドシートで管理すると、フォロー漏れを防げます。
営業活動は「数」と「質」の両輪が大切ですが、戦略的にデータを蓄積して改善を繰り返すことで、成功率が着実に上がります。
飛び込み営業は、勇気がいる一方で、地域の信頼を積み上げる非常に実践的な方法です。
誠実さ・一貫性・継続性をもって接することで、最初は断られても、やがて「また来てくれたあの人にお願いしよう」と言ってもらえる関係が築けます。
顔を合わせた“人と人との営業”こそ、長期的なビジネスの礎となるのです。
飛び込みが苦手な人向けの代替戦略
営業の世界では「直接訪問=成果が出る」と思われがちですが、実際には対面営業が苦手な人でも成果を上げる方法はいくつも存在します。
大切なのは「行動を止めないこと」と「自分に合った営業スタイルを確立すること」です。
飛び込み営業に抵抗がある場合でも、電話営業・DM配信・LINEなどのオンライン提案を上手に活用すれば、同等以上の効果を得ることが可能です。
まず、電話営業(テレアポ)は、対面営業よりも効率的に多くの見込み客へアプローチできる手法です。
リストアップした地域の店舗や法人に、短時間で的確にサービス内容を伝えられます。
電話営業で成果を上げるポイントは、「いきなり売り込まない」ことです。
最初は相手の関心を引く“問題提起型トーク”を意識しましょう。

『最近、夏場のエアコン清掃を頼むお店が増えています。貴店ではどうされていますか?』こんな感じで相手の現状に寄り添った質問から入ることで、自然な会話が生まれやすくなりますよ。
また、電話では相手の表情が見えない分、声のトーンや話すスピードが印象を左右します。
特に初対面の相手には、明るく、ゆっくりとしたテンポで話すことを意識しましょう。
次に、DM(ダイレクトメール)配信は、営業活動を効率化するもう一つの有力な手段です。
郵送だけでなく、最近ではメールやSNS広告を使ったデジタルDMも増えています。
DMの最大の利点は、「相手に考える時間を与えられる」ことです。
チラシや資料を通じて、自社のサービス内容・料金・実績をわかりやすく伝えることで、受け取った側が自分のタイミングで検討できます。
特にハウスクリーニング業の場合、清掃事例の写真や「お客様の声」を掲載すると、信頼感が一気に高まります。
DMを郵送する際は、エリアを限定する「地域セグメント戦略」を取ると効果的です。
たとえば、築10年以上の住宅が多い地域や、賃貸物件の入れ替えが活発なエリアを選ぶと、ニーズと合致しやすくなります。
郵便局の「タウンプラス」などのエリア配布サービスを利用すれば、効率的に地域密着型の営業が展開できます(出典:日本郵便「タウンプラス」 )
さらに、LINEを使った提案・フォロー営業は、現代の営業スタイルにおいて非常に重要な位置を占めています。
LINE公式アカウントを活用すれば、顧客と1対1のチャット形式でやり取りができ、見積もりや日程調整をスムーズに行えます。
また、LINEには「ステップ配信機能」や「クーポン配信機能」があるため、見込み客に定期的にアプローチする仕組みを自動化することも可能です。
例えば、「季節の清掃チェックリスト」や「年末大掃除キャンペーン情報」などを配信すれば、継続的な接点を維持できます。
これらの代替営業方法を実践する際の最大のポイントは、「定期的な接触を継続すること」です。
一度きりの連絡では印象に残りにくく、信頼も生まれません。
顧客は「忘れた頃」に再度依頼を考えることが多く、継続的な情報発信が“思い出してもらう”きっかけになります。
マーケティング理論では、顧客が商品やサービスに信頼を持つまでには「最低でも7回以上の接点が必要」とされており(いわゆる“セブンヒッツ理論”)、継続的なアプローチの重要性が裏付けられています。
また、飛び込みや電話営業を行わない場合でも、「紹介営業」を意識することは大切です。
既存の顧客に対して「お知り合いでお掃除に困っている方がいたらご紹介ください」と一言添えるだけで、紹介が生まれることがあります。
紹介は信頼の連鎖であり、広告費をかけずに高い成約率を誇る最強の営業手段の一つです。
まとめると、営業スタイルに正解はありません。
重要なのは、「どの方法を選んでも行動を止めない」ことです。
直接訪問が苦手であっても、電話・DM・LINEなど自分に合った手段で“接点を増やす仕組み”を作れば、成果は必ず積み上がっていきます。
営業とは単発の行為ではなく、信頼を築くための“継続的なコミュニケーション活動”なのです。
定期顧客を増やして安定収益を作る方法
初回対応で顧客の信頼をつかむ
ハウスクリーニングにおける初回訪問時の対応は、今後の顧客関係を左右する極めて重要な瞬間です。
初回の印象が良ければリピート率が飛躍的に上がり、逆に印象が悪ければ二度と依頼が来ないこともあります。
特に個人事業主の場合、「人=ブランド」として見られるため、営業トークよりも第一印象が最大の営業力となります。
まず意識すべきは、清潔感と誠実さが伝わる身だしなみです。
ユニフォームがある場合は常に洗濯・アイロンを施し、靴や作業道具も常に手入れをしておきましょう。
外見の清潔感は、そのまま「仕事の丁寧さ」として顧客に伝わります。
さらに、訪問時の挨拶も非常に大切です。
ドアを開けた瞬間に、明るい声で「本日はお時間いただきありがとうございます」と一言添えるだけで、安心感と信頼を与えることができます。
心理学の研究でも、人は最初の数秒で相手の印象の80%を決定すると言われており、初対面の印象形成がいかに重要かがわかります。
作業前には、作業内容と所要時間の説明を丁寧に行いましょう。
「このような流れで作業を行います」「作業時間はおよそ〇〇時間かかります」など、プロとしての視点で説明することで、顧客は“信頼できる専門家”と認識します。
作業中も、道具の扱いや動作に気を配りましょう。
掃除箇所以外の家具や床を保護するマットを敷く、ペットや小物に気を配るなどの小さな配慮が、顧客満足度を大きく左右します。
また、作業後には、仕上がりを一緒に確認する時間を取ることが重要です。
お客様の目で成果を見てもらい、気になる点があればその場で対応することで、クレームを未然に防ぐだけでなく、「最後まで責任を持ってくれる人」という信頼を得られます。
このように初回対応では、技術力以上に“人としての信頼感”が試されます。
単に作業をこなすのではなく、「この人に任せて良かった」と感じてもらえるよう、細部まで誠実さを行動で示すことが成功への第一歩です
フォローアップでリピート率を上げる
一度サービスを提供した後のフォローアップ(アフターフォロー)は、リピート率を高めるうえで欠かせない要素です。
実際、顧客が再依頼を検討するきっかけの多くは、「サービスの品質」ではなく「人の対応」にあります。
つまり、作業が完璧でも、その後の関係づくりを怠るとリピートにはつながりにくいのです。
フォローアップの第一歩は、感謝のメッセージを送ることです。
サービス提供から24時間以内に、LINEやメール、はがきで以下のような内容を送るのが理想です。
例文:
先日はハウスクリーニングをご利用いただき、誠にありがとうございました。
仕上がりにご満足いただけましたでしょうか?
もし気になる点やご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。
またのご利用を心よりお待ちしております。
このような丁寧なメッセージを送るだけで、「対応がしっかりしている」「信頼できる人だ」という印象を残せます。
メッセージの文面は、テンプレート感が出ないように軽くアレンジすることがポイントです。
顧客の名前や、作業内容を一言添えることで、よりパーソナルな印象になります。
次のステップとして、定期的なリマインドや季節キャンペーンの案内を行うと、自然に再依頼の機会を作れます。
例えば、「夏のエアコン清掃キャンペーン」や「年末の大掃除プラン」など、時期に合わせた提案を送ると、顧客は“自分のことを覚えてくれている”と感じます。
また、定期利用を促す際には、割引クーポンや「リピート特典」を用意するのも効果的です。
フォローアップで特に意識すべきなのは、「営業色を強く出さないこと」です。
あくまで顧客への“気遣い”として接することで、押し売りではなく“信頼の再構築”になります。
特にLINEを使ったフォローは、距離感が近くてもビジネスライクに保てるためおすすめです。
さらに、リピート率を上げる上で重要なのが、顧客データの記録と分析です。
いつ、どんな作業をしたか、どのタイミングで連絡したかを一覧で管理することで、フォロー時期を見極めやすくなります。
たとえば、前回の作業から3か月後に「〇〇の掃除のおすすめ時期です」と連絡を送るだけで、自然な再依頼の導線を作ることができます。
顧客フォローは単なる「お礼」ではなく、次の仕事を生むための“信頼維持活動”です。
誠実な一言と継続的な気遣いが、あなたのブランドを育て、安定したリピート顧客の基盤を築いていくのです。
定期顧客が売上を安定させる理由
ビジネスを継続的に成長させるために欠かせないのが「定期顧客(リピーター)」の存在です。
単発の依頼を積み重ねるだけでは、毎月の売上が変動し、安定した経営基盤を築くことが難しくなります。
一方、定期的にサービスを利用してくれる顧客が増えると、売上予測が立てやすくなり、経営計画や人員配置、広告投資などを計画的に行うことができるようになります。
たとえば、ハウスクリーニング業の場合、月1回や季節ごとに利用してくれる顧客が10件あれば、それだけで毎月の固定収入が見込めます。
仮に1件あたりの単価が1万円でも、10件で10万円の安定収入になります。
これが20件、30件と増えれば、売上の“土台”ができ、景気変動や一時的な需要減の影響を受けにくくなります。
実際に、総務省の「サービス産業動向調査」でも、清掃・家事代行業などの生活関連サービスにおいて、リピーターが売上の過半を占める傾向が報告されています(出典:総務省統計局『サービス産業動向調査』)
また、定期顧客が増える最大の利点は、**「新規顧客の獲得コストを抑えられる」**ことです。
広告やポスティングなどで新規顧客を獲得するには、1件あたり数千円〜1万円程度のコストがかかる場合がありますが、既存顧客のリピートを促すだけなら、コストはほぼゼロです。
結果として、利益率が向上し、経営の効率化にもつながります。
さらに、定期的に同じ顧客と接することで、サービス品質を高めるためのフィードバックが得やすくなります。
顧客のライフスタイルや要望の変化を直接聞くことができるため、サービスの改善や新メニュー開発にも役立ちます。
たとえば、「小さなお子さんがいる家庭には、低刺激の洗剤を使用する」「高齢者宅では家具移動のサポートを提案する」など、顧客特性に合わせたカスタマイズが可能です。
このように、定期顧客は単なる「売上源」ではなく、「安定収益」「顧客理解」「サービス向上」のすべてを支える存在です。
リピート契約を増やすことは、安定した収益構造を築くだけでなく、長期的な顧客満足を実現する最も効果的な経営戦略なのです。
顧客管理を仕組み化する
安定した顧客基盤を築くためには、日々の営業活動を「勘」や「記憶」に頼らず、仕組みとして管理することが不可欠です。
特にハウスクリーニング業や訪問サービス業では、顧客ごとに住所や作業履歴、好み、注意点などの細かい情報を正確に把握しておくことで、リピート率を飛躍的に高めることができます。
顧客情報は、まずはExcelやGoogleスプレッドシートなどの無料ツールで十分に管理可能です。
特別なシステムを導入しなくても、次のような項目を整えておくことで、必要な情報を瞬時に把握できます。
顧客管理の基本項目例:
- 名前・住所・電話番号
- 利用日・作業内容
- 次回提案時期(例:3か月後にエアコン清掃の提案)
- 特記事項(例:ペット有/香料のある洗剤NG/家族構成など)
- 紹介元(どのルートから来た顧客か)
-
対応履歴(電話、LINE、訪問などの連絡記録)
このような情報を整理しておくと、フォローアップのタイミングを逃さず提案できるようになります。
たとえば、前回の清掃から3か月後に「そろそろエアコン内部の汚れが気になる頃ではありませんか?」といったメッセージを送ることで、自然な形で再依頼を促せます。
顧客側から見ても、「自分の状況を理解してくれている」と感じ、安心感と信頼感が生まれます。
さらに、スプレッドシートを活用すれば、条件付き書式やフィルター機能で「3か月以上経過した顧客のみを表示」などの自動抽出も可能です。
これにより、フォロー漏れを防ぎ、効率的に営業活動を行えます。
顧客数が増えてきた場合は、CRM(顧客管理システム)や無料の顧客管理アプリへの移行も検討すると良いでしょう。
これにより、スマートフォンからも即時に顧客情報を確認でき、外出中の対応力が向上します。
また、顧客管理を仕組み化する目的は「データをためること」ではなく、“次の提案につなげるための行動データ”を作ることです。
顧客のニーズや過去のやり取りを蓄積しておけば、提案内容を個別最適化できるため、成約率が大幅に上がります。
例えば、「前回はキッチン中心の清掃を依頼した方に、今回は換気扇やレンジフードのセット割を提案する」といった応用が可能です。
最後に、管理データは定期的に見直し・更新することが大切です。
住所変更、家族構成の変化、ライフスタイルの変化など、顧客の環境は常に変わります。
年に数回、顧客リストを見直して最新情報に保つことで、タイムリーで的確な提案ができるようになります。
このように、顧客管理を“人ではなく仕組みで回す”ことは、営業効率を高めるだけでなく、リピーターを増やし、結果的に事業の安定化へと直結します。
顧客データを戦略的に扱うことが、ハウスクリーニング事業を持続的に成長させる鍵なのです。
リピート率を高める特典づくり
顧客に「またお願いしたい」と思ってもらうためには、価格や技術力だけでなく、心理的な満足感を与える仕組みづくりが重要です。
その代表的な手段が「リピート特典」や「紹介特典」です。
これは単なる割引制度ではなく、顧客との関係性を深め、継続利用を自然に促すマーケティング戦略の一つといえます。
例えば、「3回目の利用で10%OFF」「友人紹介で双方に500円ギフト券プレゼント」といった特典は、金額的には小さくても心理的なインセンティブとして非常に効果的です。
ハウスクリーニング業においては、以下のような特典構成が特に効果的です。
◆ リピート顧客向けの特典例
- 3回利用で「次回10%OFF」または「ガラスクリーニング無料」など
- 6回利用で「定期プラン特別会員」への昇格(優先予約・限定クーポン配布など)
-
利用後アンケート回答で「次回500円OFF」
◆ 紹介特典の導入例
- 紹介した方:500円OFF/紹介された方:初回10%OFF
-
紹介回数に応じて「プチギフト」「洗剤セット」などを進呈
このような制度を導入する際のポイントは、「ルールをわかりやすく」「申請手続きを簡単にする」ことです。
特典内容が複雑だったり、条件が不明確だったりすると、顧客は利用をためらいます。
紙のチラシやLINE公式アカウントのメッセージで、特典の概要と利用方法を明確に案内しましょう。
さらに、季節限定キャンペーンを組み合わせることで、利用頻度を上げることができます。
たとえば、年末の大掃除前、梅雨入り前、花粉シーズンなど、生活リズムと密接に関係する時期を狙うことで、顧客の“必要性”を刺激できます。
季節キャンペーンの一例:
- 年末「まとめて大掃除キャンペーン」:3部屋セットで1万円OFF
- 梅雨前「カビ・湿気対策キャンペーン」:浴室・エアコン同時割引
-
春先「花粉対策クリーンパック」:空気清浄・換気口清掃付き
また、こうした特典制度を単発で終わらせるのではなく、顧客データと連携して自動的に案内できる仕組み化を行うとさらに効果が上がります。
ExcelやLINE公式アカウントのタグ機能を活用すれば、特定の時期にだけ特定顧客へ自動通知が可能です。
これにより、「お得だから利用しよう」という自発的な再依頼が増えます。
リピート特典とは、単に“割引を与える仕組み”ではなく、“次の接点を作る仕組み”です。
顧客に「またお願いしたい」「この人を誰かに紹介したい」と感じてもらうような温かみのある制度設計こそが、長期的なリピート率向上の鍵となります。
顧客との関係を長く続けるコツ
どんなに魅力的な特典制度や販促施策を導入しても、最終的に顧客がリピートする理由は「信頼」です。
サービス業における顧客ロイヤルティ(信頼と継続意向)の根幹は、「技術力 × 誠実な対応 × 感情的つながり」で成り立っています。
つまり、価格競争ではなく、“人としての信頼”を得ることが長期的な成功の鍵になります。
まず意識したいのは、無理な営業をしないことです。
過剰なセールストークや頻繁な販促メッセージは、顧客に「売り込み感」を与え、逆効果になる場合があります。
代わりに、「お困りごとはありませんか?」「この季節はエアコンの汚れが出やすいですよ」といった“気づかい型コミュニケーション”を意識しましょう。
顧客の生活を理解し、必要なタイミングでさりげなく提案することが、信頼関係を育みます。
次に重要なのが、感謝の姿勢を常に言葉にすることです。
作業終了後の「本日はありがとうございました」に加え、後日のフォローアップメッセージで「またお会いできる日を楽しみにしております」と添えるだけでも、顧客の印象は格段に変わります。
心理学的にも、人は自分を大切に扱ってくれる相手に好意を抱きやすいとされており(出典:日本心理学会)、こうした小さな言葉の積み重ねが“信頼資産”を築きます。
また、長期的な関係を保つためには、「記録」と「一貫性」も欠かせません。
顧客ごとの要望や過去の作業内容を管理しておくことで、次回以降の対応精度が上がり、「覚えていてくれたんだ」と感動を与えることができます。
特に高齢者や忙しい家庭では、「前回と同じようにお願いします」という依頼が多く、一貫した品質提供がリピートの決め手になります。
最後に、口コミを自然に生む関係性づくりも意識しましょう。
満足した顧客は、自発的に知人へサービスを紹介してくれることがあります。
しかし、そのためには「紹介したくなる人柄」「安心して任せられる対応」が必要です。
たとえば、作業後に「もし周りでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください」と一言添えるだけで、紹介のきっかけが生まれます。
顧客との関係性は、短期的な売上ではなく、信頼を積み上げる長期投資です。
派手なキャンペーンや値引きよりも、「この人なら間違いない」と思ってもらう誠実な姿勢こそが、最強の営業戦略です。
そして、その積み重ねが、やがて安定したリピート顧客と口コミ紹介という“強固な経営基盤”を形成していくのです。
まとめ:継続こそ最大の営業力
この記事をまとめます。
- 地域に密着した活動が顧客からの信頼を生む
- チラシはターゲット設定とデザインで反応率が変わる
- 配布エリアと時期を戦略的に決めることで効率化できる
- ホームページのSEO対策が24時間の集客装置になる
- 施工事例や口コミ掲載で信頼性と成約率を高められる
- SNS発信でファン層を広げ口コミを自然に拡散できる
- マッチングサイト活用で効率的に新規顧客と出会える
- 飛び込み営業は信頼構築と地域認知に最も効果的である
- 営業が苦手でもLINEやDMで継続的接点を作れる
- 初回対応での印象がリピート率を大きく左右する
- フォローアップの一言が定期契約獲得のきっかけになる
- 定期顧客の存在が売上を安定させ経営を強くする
- 顧客情報を整理管理することで最適な提案が可能になる
- リピート特典や紹介制度が継続利用を自然に促進する
- 信頼と誠実さを積み重ねることが最大の営業力となる

「この人にお願いしたい」と思われる存在になれば、自然と顧客は増えていきます。
利益は信頼のあとに必ずついてきます。焦らず、一歩ずつ積み重ねていきましょう。
\実際に現場で使っているハウスクリーニングおすすめ洗剤&道具/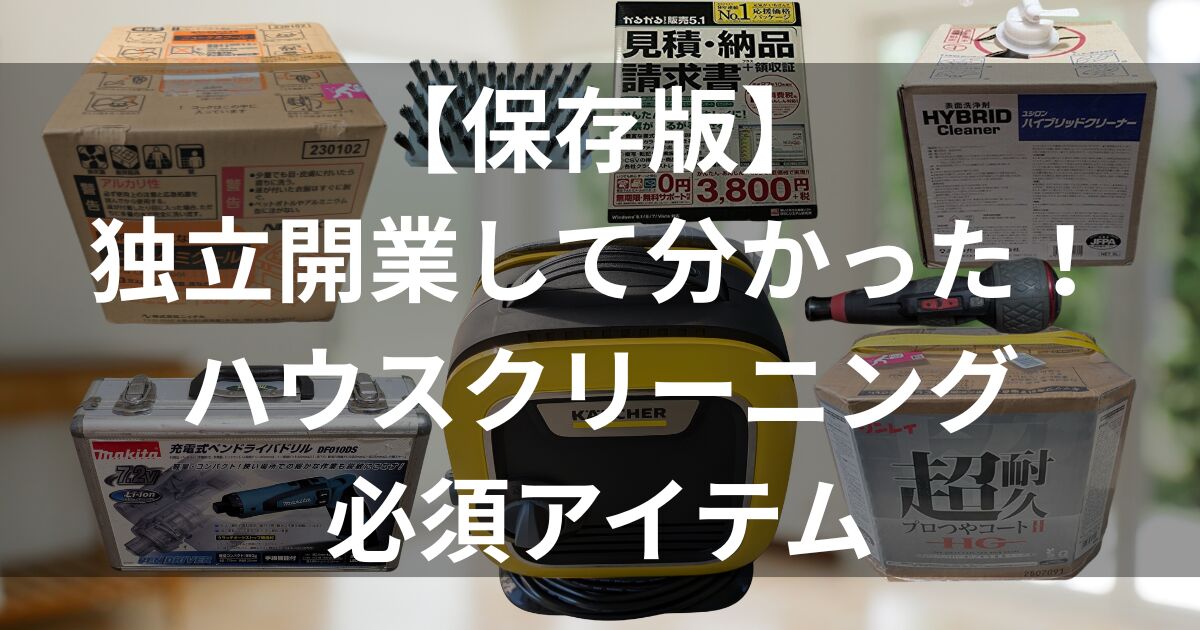
独立開業を目指すとき、最初に悩むのが「どんな洗剤や道具を揃えればいいのか」「経理や顧客管理はどうするのか」、そして「一人で不安になったときに頼れる場所があるのか」という点ではないでしょうか。
私自身、開業当初は同じように迷い、必要のないものを買ってしまったり、逆に本当に必要な道具が抜けていて現場で困った経験があります。
また、事務作業に追われて時間を失ったり、孤独感に押しつぶされそうになったこともありました。
そうした失敗や試行錯誤を経て、「これだけは導入してよかった」と胸を張っておすすめできるものがいくつかあります。
それが 『洗剤・道具・会計ソフト・コミュニティ 』の4つです。
これらを揃えることで、作業効率が大きく向上し、顧客からの信頼も得られ、さらには安心して長く続けられる基盤が整いました。

私が現場で実際に使って「これは間違いなく役に立つ」と感じたものだけをまとめました。これから独立開業される方の参考になると思いますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
👉 『【保存版】独立開業して分かった!ハウスクリーニング必須アイテム』を詳しく見る
【この記事を書いた人】

清掃業歴20年以上、累計1万件以上の現場を経験。
大手清掃会社に14年間勤務し、現場管理やスタッフ育成、顧客対応を通じて豊富なノウハウを習得。
42歳で独立後は、住宅・オフィス・店舗清掃を中心に活動中。
このブログでは、清掃業での独立ノウハウ、集客術、現場トラブル解決法などを実体験に基づいて発信しています。