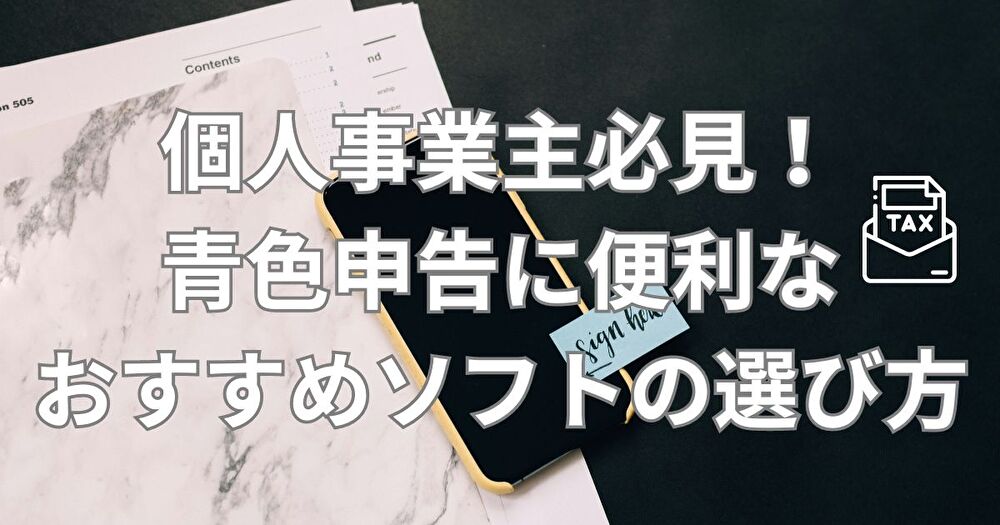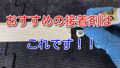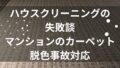執筆:ヒデ(清掃業歴20年以上・現場経験1万件超)|プロフィール

-
青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきかが分からない
-
青色申告を始めるための準備や必要な手続きが分からない
-
どの青色申告ソフトを選べばよいか判断できないな
-
申告作業を効率化して正確にできるか不安だ
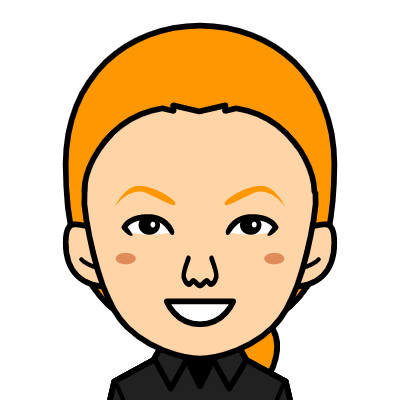
こういう悩みにお答えします。
『個人事業主 青色申告 おすすめ』と検索している方は、どの申告方法を選ぶべきか、どのソフトが自分に合うのかで迷いやすいものです。
本記事では、青色申告と白色申告の違いを押さえたうえで、青色申告を始めるために必要な準備を整理し、青色申告ソフトの種類の特徴を踏まえて比較します。
さらに、青色申告ソフトの比較表で主要サービスの強みを俯瞰し、青色申告ソフト選びのチェックリストで失敗や後悔を避ける観点を提示します。
最後に、個人事業主におすすめの青色申告ソフト3選を具体的に紹介し、スムーズで正確な申告につなげます。
【この記事で分かること】
-
青色申告と白色申告の基本とメリットの整理
-
青色申告開始までの必要手続きと流れ
-
ソフト選びの判断軸と主要サービスの比較
-
自分に合うソフトを選ぶための実践的ポイント
個人事業主におすすめの青色申告とは
確定申告の基本と申告時期
個人事業主にとって、確定申告は毎年欠かせない大切な手続きです。
1月1日から12月31日までの1年間の収入や経費を整理し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ申告と納税を行います。
会社員は年末調整で税金が処理されることが多いですが、個人事業主は自分で売上や経費をまとめ、申告書を作成して提出しなければなりません。
申告の方法には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は帳簿のつけ方が少し難しいかわりに、最大65万円の控除や赤字を翌年以降に繰り越せるなど、税金を減らすためのメリットが豊富です。
白色申告は手続きがシンプルで始めやすいですが、節税のメリットはあまりありません。事業が軌道に乗るほど、青色申告の良さを実感できる場面が増えていきます。
期限を守らずに遅れてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティがかかることもあります。だからこそ、日ごろから証拠となる書類を整理し、毎月の帳簿をコツコツ進めておくのが安心です。

【申告スケジュールの押さえどころ】
- 期間内の取引証憑の整理と帳簿記帳を通年で進めます
- 年度末に決算仕訳・残高確認・決算書作成を行います
- 申告期間に確定申告書Bと青色申告決算書を提出します
毎月の領収書や通帳を整理しておくと、年度末に慌てる必要がありません。
特に12月は、売れ残った商品を数える「棚卸」や、設備の購入・廃棄の確認など、1年のまとめ作業が増える時期です。
年明けから2月上旬にかけては、減価償却費の計算や家事按分(仕事とプライベートを分ける処理)の見直しを済ませ、2月中旬から始まる申告期間にすぐ出せる状態にしておきましょう。
もし電子申告(e-Tax)を使う場合は、マイナンバーカードの有効期限やカードリーダーの準備も忘れずに確認しておくと安心です。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の大きな違いは、「手間」と「節税効果」のバランスにあります。
青色申告は複式簿記という少し複雑な帳簿をつける必要がありますが、その代わりに最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
さらに、赤字を3年間繰り越せる仕組みや、家族に支払った給与を経費にできる制度など、長く事業を続ける人にとってうれしい特典がたくさんあります。
一方の白色申告は、単式簿記で記録できるので簡単に取り組めますが、特別な控除はなく、節税の効果はあまり期待できません。
そのため、事業を大きくしていきたい人や経費を多く計上したい人には物足りない方法と言えます。
最近では会計ソフトを使えば、自動で仕訳や帳簿をつけてくれるため、青色申告の難しさもかなり軽減できます。
こうしたツールを活用すれば、青色申告のハードルはぐっと下がり、安心して節税メリットを受けられるようになります。

長いこと商売続けるつもりじゃったらのう、青色申告にしときんさいや
青色申告特別控除の要点
青色申告の最大の魅力のひとつが「青色申告特別控除」です。
これは、正しい帳簿付けや書類の提出を行うことで、所得から最大65万円を差し引くことができる制度です。差し引かれた分だけ課税所得が減るため、最終的に納める税金も少なくなります。
例えば課税所得が300万円の場合、65万円の控除を受ければ課税対象は235万円となり、税負担が大きく軽くなる計算です。
控除額は一律ではなく、条件によって10万円、55万円、65万円の3段階に分かれています。
- 10万円控除は、簡易帳簿(単式簿記)による記帳を行った場合
- 55万円控除は、複式簿記での仕訳と総勘定元帳の作成、損益計算書や貸借対照表を添付した場合
- 65万円控除は、55万円控除の条件を満たしたうえで、電子申告(e-Tax)で提出するか、または電子帳簿保存法に対応した保存を行った場合に適用されます
つまり、より正確で手間のかかる記帳を行い、さらに電子申告や電子帳簿保存を活用するほど控除額が大きくなる仕組みです。
この控除を受けるには、毎日の記帳を正確に続けることが欠かせません。
年末にまとめて入力するのではなく、日々の取引をコツコツと仕訳し、領収書や請求書を整理しておくことが、決算時の混乱を防ぎます。
また、複式簿記の知識がない場合でも、会計ソフトを導入することで自動仕訳やレポート作成が可能となり、控除の取りこぼしを防げます。
税制は改正されることも多いため、常に最新の条件を確認しておくことも忘れてはいけません。
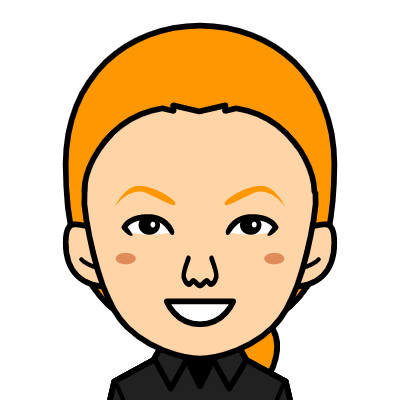
控除額の条件とか詳しい内容については、国税庁がちゃんと公表してますよ。(出典:国税庁「青色申告特別控除」
以上を踏まえると、青色申告特別控除を最大限活用するためには、早い段階で会計ソフトを導入し、証憑のデジタル管理や自動仕訳を取り入れることが賢明です。
青色申告を始めるために必要な準備
青色申告を利用するには、いくつかの準備が必要です。
最初のステップは、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することです。
これは開業届を提出した後に行う手続きで、青色申告を利用したい年の3月15日までに申請しなければなりません。この期限を過ぎると、その年は青色申告を選ぶことができないため注意が必要です。
承認を受けるだけでなく、スムーズに青色申告を運用するためには、帳簿付けや資料整理の体制を整えることが大切です。
事業を始めたばかりの時期こそ、こうした仕組みを整えておくと後々の作業が楽になります。
【準備のステップ】
-
会計方針の決定と勘定科目の整理:どのような費用をどの科目に仕訳するかを最初に決めておくと、ブレのない帳簿管理ができます。
-
領収書・請求書・通帳明細の保管ルール策定:紙のまま保管するのか、スキャンして電子保存するのかをあらかじめ決めると、証憑整理がスムーズです。
-
会計ソフトの選定と初期設定(事業者情報・科目・開始残高):多くのソフトには青色申告用のフォーマットが備わっているため、初期設定をしっかり行えばその後の記帳作業が効率化されます。
-
月次の記帳サイクルと決算スケジュールの明文化:毎月のどのタイミングで記帳するのか、決算時にどの作業を行うのかをルール化しておくと、作業の漏れを防げます。
こうした準備を文書としてまとめておくと、年度が変わっても同じルールで運用できるため安心です。
特に開業初期は慣れない作業が多いため、最初に手順を整え、会計ソフトなどのツールを導入しておくことが、長期的に大きな助けとなります。

会計ソフトを使えば、この流れを大幅に効率化できますよ。
青色申告ソフトの種類
青色申告に対応したソフトは、大きくクラウド型とインストール型の2種類に分けられます。
それぞれの仕組みや特徴を理解することで、自分の業務スタイルに合ったソフトを選ぶことができます。
クラウド型は、インターネットに接続できる環境さえあれば、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからも利用できる点が強みです。
特に、銀行口座やクレジットカード、さらには請求書発行サービスとの自動連携機能があるため、日々の入力作業を大幅に減らせます。
また、データはベンダー側で自動的にバックアップされるため、万が一パソコンが故障しても情報が失われる心配がありません。
加えて、税制改正があった際にはベンダーが即座にアップデートを行ってくれるため、常に最新のルールで申告作業を進められます。
一方、インストール型はソフトを自分のパソコンに直接入れて使うタイプで、インターネットに接続しなくても利用できるのが特徴です。
地方やネット環境が安定しない場所で仕事をしている人にとって、オフラインで作業できる安心感は大きなメリットです。
さらに、データを自分のパソコン内に保存できるため、情報を完全に手元で管理できるという安心感もあります。
動作の安定性も高く、通信状況に左右されないため、集中して作業を進めたい人に適しています。
ただし、バックアップは自分で行う必要があり、税制改正の際はソフトのアップデートを手動で適用する手間がかかります。
このように、クラウド型は「利便性と自動化」を重視したい人、インストール型は「安定性と自分での管理」を優先したい人に向いています。
自身の作業環境や業務スタイルを踏まえて、どちらを選ぶか検討することが大切です。

外出先でも作業する人はクラウド型、オフライン利用が多い人はインストール型がおすすめだよ。
個人事業主におすすめの青色申告ソフトを比較
クラウド型とインストール型比較
クラウド型とインストール型には、それぞれの利点と注意点があり、選択によって日常の会計業務の流れやコストにも違いが出ます。
以下の表は両者の特徴を整理したものです。
| 観点 | クラウド型 | インストール型 |
|---|---|---|
| 利用環境 | ブラウザやアプリから即時利用可能。外出先や複数デバイスからアクセス可 | 専用PCでのみ利用。利用端末に依存 |
| データ連携 | 銀行・カード・請求書サービスと自動連携。入力作業を削減 | 外部サービスとの連携は手動設定が中心 |
| バックアップ | 自動バックアップで復元容易。データ消失リスク低減 | 自前で定期バックアップが必要。手間と管理コストが発生 |
| 税制改正対応 | ベンダー側が自動で反映。常に最新の制度に対応 | ユーザーがアップデートを手動適用。対応遅れのリスクあり |
| オフライン可用性 | 通信環境に依存。ネット接続が必須 | オフラインでも利用可能。通信環境に影響されない |
| セキュリティ方針 | ベンダーのセキュリティ基準に準拠。高度な暗号化やアクセス管理を提供 | 自社や個人のルールで管理。セキュリティ水準は運用方法に依存 |
表からもわかるように、クラウド型は利便性と自動化に優れ、日々の作業を効率化したい人におすすめです。
一方、インストール型はオフライン利用やデータを完全に自己管理したい人に適しています。
特に注意すべきはセキュリティの考え方です。
クラウド型はベンダーが高度なセキュリティ対策を施している一方で、データがインターネット上に保存されるため、不安を感じる人もいるかもしれません。
一方、インストール型は自分でセキュリティを管理できる反面、その責任もすべて自分にあります。
したがって、ネット環境や業務スタイル、セキュリティへの考え方を踏まえて選ぶことが大切です。
公的な制度改正やITセキュリティ基準については、経済産業省や総務省などの公式情報を参考にすると安心です(出典:経済産業省「情報セキュリティ政策」 )
青色申告ソフトの比較表
青色申告ソフトを導入する際には、どのサービスが自分の業務スタイルに合っているかを冷静に比較することが大切です。
特にクラウド型ソフトは、各社ごとに強みや特徴が大きく異なります。
以下の表では、主要なクラウド型サービスを並べ、操作性や自動化機能、連携の幅といった観点から整理しました。
| ソフト名 | 主な特徴 | 無料体験 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| やよいの青色申告オンライン |
画面が直感的で分かりやすく、確定申告書の自動作成に強い。初心者にやさしい設計。 | あり | 初めて青色申告に挑戦し、操作性を重視する人 |
| freee会計 |
銀行・カードとの連携が強力で、AIによる自動仕訳が充実。スマホアプリの操作感が良好。 | あり | 外出先での経理や日々の記帳を効率化したい人 |
| マネーフォワードクラウド確定申告 |
自動仕訳の精度に定評があり、複数口座や多様なサービスとの連携が豊富。 | あり | 複数の収入源を一元管理したい人やデータ連携を重視する人 |
各ソフトは共通して無料体験が提供されているため、実際に操作してみることが選定の第一歩です。
ソフトウェアの利用感覚は人によって大きく異なるため、導入前に試すことで「思ったよりも操作が複雑」「スマホ入力が快適」といった印象を事前に確認できます。
要するに、初めて青色申告を行う人はやよい、スマートフォン中心で手軽に入力したい人はfreee、連携機能をフル活用したい人はマネーフォワードが有力な候補となります。
公式サイトでも機能の違いが詳しく掲載されているため、比較検討の際は必ずチェックすることが推奨されます。

すべて無料体験が可能なので、まずは試してみるのが安心ですよ。
青色申告ソフト選びのチェックリスト
青色申告ソフトは一度導入すると数年間は同じ環境を使い続けるケースが多いため、選定段階での見極めがとても重要です。
特に自分の事業に合った機能が備わっているかどうかで、日々の経理作業の負担や確定申告期のスムーズさが大きく変わります。
以下の表をチェックリストとして活用し、導入前に確認しておきましょう。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 青色申告特別控除対応 | 複式簿記に対応し、決算書や申告書を自動作成できるか |
| 金融機関連携 | 銀行・カード・電子マネーなどのデータを自動取得できるか |
| 自動仕訳 | AI学習機能や推奨仕訳の精度、修正のしやすさ |
| モバイル対応 | スマホアプリでの入力やレシート撮影機能の有無 |
| サポート体制 | チャット、電話、ヘルプ記事の充実度や対応時間 |
| データ移行 | 他社ソフトやExcelからの移行方法が用意されているか |
| 料金と更新 | 年額・月額の料金体系と将来的な拡張性 |
| セキュリティ | 二要素認証やアクセス権限の管理機能が備わっているか |
| バックアップ | データの復元方法や履歴管理が可能か |
| 税制改正対応 | 法改正時に迅速にアップデートされる仕組みがあるか |
このように多角的に確認しておくことで、導入後に「欲しい機能がなかった」「サポートが不十分だった」といった不満を防げます。
とくに無料体験を活用して、実際の操作画面で入力のしやすさを確認することは欠かせません。
また、サポート窓口に事前に問い合わせて、回答のスピードや内容の的確さを体感するのも有効です。
以上のステップを踏めば、自分の事業にとって最適なソフトを選び、長期的に安心して運用することができます。
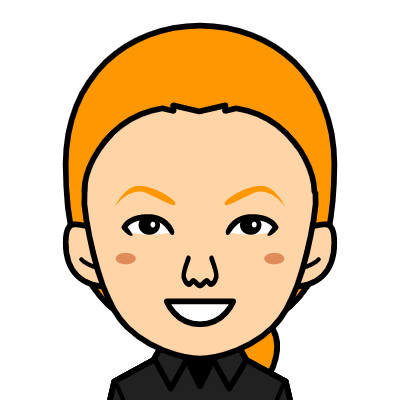
「まあこれでええか」って適当に決めたら後で泣くことになるけど、このチェックリストさえ押さえとったら心配いらないですよ。
個人事業主におすすめの青色申告ソフト3選
青色申告を効率的に進めるためには、自分の事業規模や作業スタイルに合った会計ソフトを導入することが欠かせません。
現在の主要サービスは、初心者向けの操作性に優れたものから、自動化や連携に強みを持つものまで多様です。
ここでは、特に利用者数が多く、機能面でも信頼性の高い3つのクラウド型サービスを紹介します。
いずれのサービスも無料体験が用意されているため、まずは実際の入力画面を触ってみることが、失敗のない選定につながります。
1,やよいの青色申告オンライン

やよいの青色申告オンラインは、操作画面がシンプルでわかりやすく、初めて青色申告に取り組む個人事業主でも迷わず進められる設計が特長です。
確定申告書や青色申告決算書を自動で作成してくれる機能が充実しており、複式簿記に不慣れな人にとっても安心して使える仕組みになっています。
特に初期設定はガイドが丁寧で、事業者情報や勘定科目の登録がスムーズに行えるため、学習コストを大きく抑えられます。
さらに、証憑書類をスマホで撮影して取り込む機能や、仕訳テンプレートの活用により、毎月の処理をパターン化しやすいのも魅力です。
これによって月次処理の再現性が高まり、決算時に慌てることなく準備が整います。
小規模事業者や初めて青色申告に挑戦する人には特に適した選択肢といえるでしょう。
👉 やよいの青色申告オンライン を無料で試す
2,freee会計

freee会計は、銀行口座やクレジットカードとの自動連携に強みがあり、明細を自動で取り込んで仕訳までつなげられる点が評価されています。
AIを活用した仕訳提案機能は、入力の手間を減らすだけでなく、記帳の正確性も高めてくれます。
スマホアプリの完成度も高く、レシート撮影や外出先からの入力が容易にできるため、パソコンを開く時間がなかなか取れない人でも日常的に使いやすい設計です。
また、日々の経理業務をワークフローとしてルール化すれば、1日数分の作業で記帳を終えられるケースもあります。
効率を重視するフリーランスや、外回りの多い事業者にとって、freee会計は作業の時短と自動化を両立できる強力な選択肢といえます。
3,マネーフォワードクラウド確定申告

マネーフォワードクラウド確定申告は、自動仕訳の精度が高く、複数の銀行口座やクレジットカードを一括で管理できる点が大きな魅力です。
売上や経費の管理を部門別・品目別に細かく分類できるため、日々の会計処理がそのまま経営分析や節税検討に活かせるのも特徴です。
対応している連携サービスの数も多く、ECサイトや決済サービス、クラウド請求書ソフトなど、幅広い外部サービスとデータを統合できます。
そのため、複数の収入源を持つ事業者や、デジタルサービスを組み合わせて事業を運営している人にとって、非常に相性の良いソフトといえます。
マネーフォワードは法人向けサービスも展開しているため、将来的に法人化を検討している事業者にとっても、スムーズな移行を見据えた選択肢として安心感があります。
公式情報では常に最新の税制対応が案内されており、安心して使える体制が整えられています。
個人事業主におすすめの青色申告ソフト まとめ
-
青色申告は記帳要件と引き換えに控除が充実
-
申告期間は毎年2月16日から3月15日まで
-
青色申告承認申請書の提出を早めに計画する
-
複式簿記と決算書作成はソフト活用で効率化
-
クラウド型は自動連携と保守省力化に強み
-
インストール型はオフライン環境でも安定運用
-
やよいは初学者に扱いやすく申告作成が容易
-
freeeはモバイル入力と連携の快適さが魅力
-
マネーフォワードは自動仕訳と連携範囲が広い
-
チェックリストで要件と運用負担を可視化する
-
金融機関連携と自動仕訳の精度を重視して選ぶ
-
サポート対応とヘルプの充実度を事前に確認する
-
バックアップとセキュリティの方針を明確にする
-
無料体験で操作感と導入後の流れを検証する
-
個人事業主 青色申告 おすすめはソフト導入で実現する
【この記事を書いた人】

清掃業歴20年以上、10000件以上の現場経験あり。
住宅からオフィスまで多様な現場で実績を積んできたヒデです。
42歳で独立し、開業準備から営業・税務・顧客対応まで経験しました。
このブログでは、独立ノウハウや集客術、現場トラブル解決法を一次情報として発信し、同じ道を目指す方への実践的な指針を提供しています。