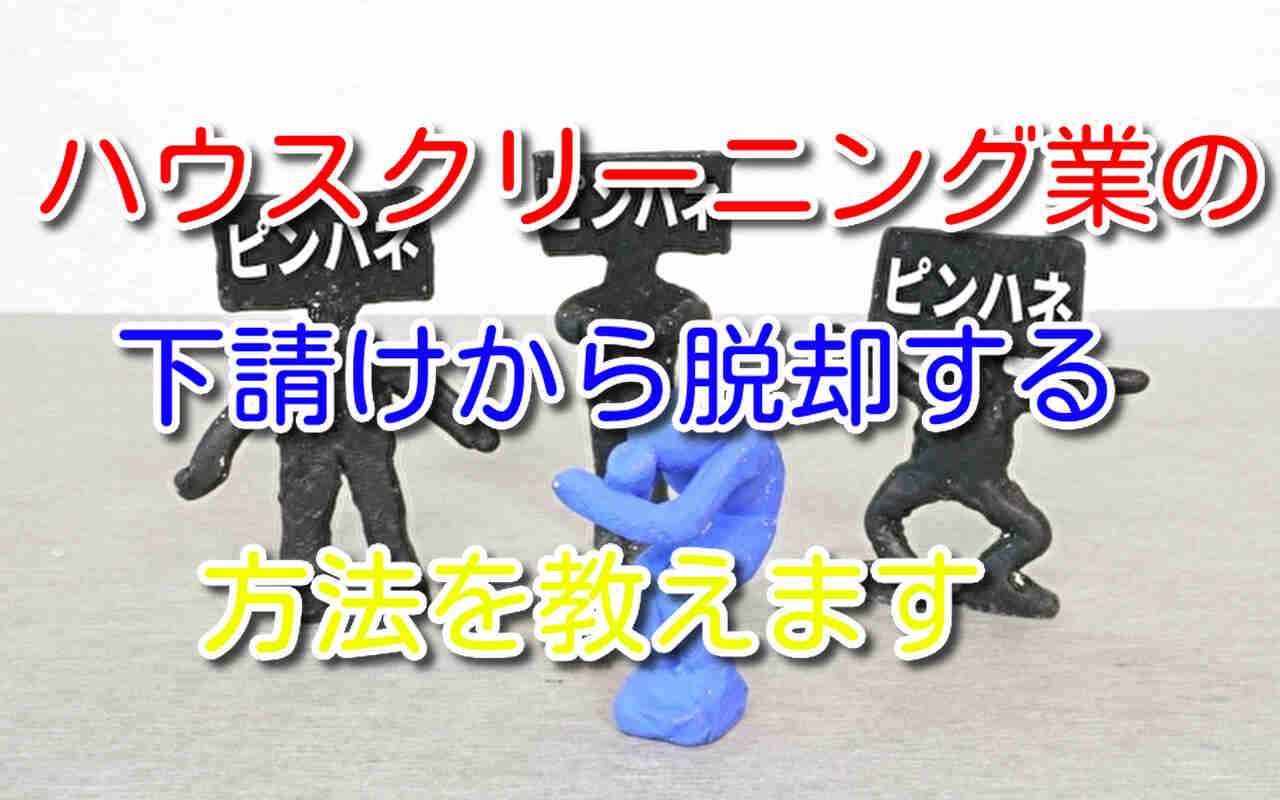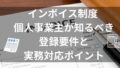- 下請けの空室清掃ばかりしている
- 安い金額で請け負っているのでやる気がいまいち
- 下請けの現場で忙しいのに全然儲からない
- 下請けからの脱却の仕方を教えて

このような悩みにお答えします
ハウスクリーニング 下請けで検索している方の多くは、「一生懸命やっているのに儲からない」「仕事量のわりに手元にお金が残らない」といった悩みを抱えています。
下請けには良い面もありますが、長い目で見るとデメリットの方が大きいのも事実です。
この記事では、下請けのメリット・デメリットを整理しつつ、下請けから脱却する方法をわかりやすく解説します。
営業や集客の工夫を通じて、安心して選ばれるお店を作るためのヒントをまとめています。

無理なく直請けの仕事を増やし、安定した収入と自由な働き方を目指しましょう
【この記事を読んでわかること】
- ハウスクリーニングの下請け構造と儲かりにくい理由が分かる
- 直請けと下請けの利益の差とリスクの違いを理解できる
- 無理なく下請けから脱却していく具体的なステップがイメージできる
- ホームページや名刺・チラシを使った直請け集客のコツが分かる
ハウスクリーニング 下請けの実態と課題
下請けのメリット・デメリットを整理する
ハウスクリーニング業界において下請けの仕事を受けることは、多くの事業者が独立初期に選ぶ現実的なスタート地点です。
元請けから案件が安定的に供給されるため、営業活動をしなくても一定の仕事を確保できるという点は大きな安心材料になります。
特に、独立したてで顧客基盤がない場合や資金に余裕がない場合、下請けは「とりあえず仕事がある」という状況を作りやすいのが利点です。
また、見積もりや集客の手間が省けるため、掃除業務そのものに集中できる点もメリットとして挙げられます。
例えば、新規集客にかかるコスト(チラシ制作費、広告出稿費、Webサイト制作費など)は自社で営業する場合に避けて通れませんが、下請けではその負担を最小限にできます。
しかし同時に、下請けには大きな制約も存在します。
代表的なデメリットは以下の通りです。
特に単価の低さは経営を圧迫しやすく、同じ時間働いても収入が直請けより少なくなります。
このため「仕事量は多いのに貯金ができない」「体力的に限界なのに売上は伸びない」といった悩みに直結します。
こうした状況を踏まえると、下請けは短期的には役立つ選択肢ですが、長期的に持続可能な経営を目指すのであれば依存しすぎるのは避けるべきだと考えられます。
低価格受注が利益を圧迫する理由
下請けの構造では、元請けが顧客から受け取った金額の大部分を取り、実際に現場で作業する下請け事業者には残りが支払われます。
例えば、エアコンクリーニング1台につき顧客が10,000円を支払っても、下請けに渡る金額は4,000円程度にとどまるケースが一般的です。この時点で売上の半分以上を失っていることになります。
さらに、ここから移動にかかるガソリン代、駐車場代、清掃道具や洗剤の消耗品費用などの経費が差し引かれるため、手元に残る利益はごくわずかです。
繁忙期には移動距離や作業件数が増えますが、その分経費も膨らみ、働いた時間に見合う収入を得られない状況が生まれやすいのです。
また、元請けの価格決定権が強いため、下請けは値上げ交渉が難しく、単価が数年間据え置かれることも珍しくありません。
その間に資材価格や燃料費、人件費が上昇すると、利益率はさらに圧迫されていきます。
直請けと下請けの違い(イメージ)
| 項目 | 直請け | 下請け |
|---|---|---|
| 料金を決める権利 | 自分にある | 元請けにある |
| 単価 | 高めに設定できる | 安くなりがち |
| お客さんとの関係 | 自分に残る | 元請けが持つ |
| 利益 | 高くなりやすい | 少なくなりやすい |

この表からも明らかなように、直請けと下請けでは同じ時間働いても利益に大きな差が出ることがわかりますね。
直請けは顧客との関係性を積み重ねることでリピートや紹介につながり、さらに利益を安定化させやすい一方で、下請けは努力しても利益が伸びにくい仕組みとなっています。
労働時間と収入のバランスを考えれば、下請け依存を続けるリスクは高く、脱却のための準備が必要になると考えられます。(出典:総務省統計局『労働力調査』 )
下請け依存が経営を不安定にする背景
下請けに大きく依存している状態は、見かけ上は「常に仕事がある」ように見えても、実際には非常に不安定な経営環境を生みやすいと考えられます。
理由の一つは、単価や条件を元請けに大きく握られてしまうことです。
元請けが業績悪化や価格競争に直面すれば、そのしわ寄せは下請けに直接跳ね返り、突然の単価引き下げや案件の減少につながります。
さらに、顧客との接点が元請けに集中するため、自社には顧客情報や口コミが蓄積されません。
その結果、長期的な紹介やリピートにつながらず、自分で仕事を生み出す力を育てにくいという課題も残ります。
こうした状況では、「仕事は忙しいのに利益は残らない」「来月の予定がどうなるか読めない」といったストレスを抱える経営者が増えやすいのです。
実際、中小規模の事業者は取引先依存度が高いほどリスクが大きいことが指摘されています。
たとえば中小企業庁の調査でも、特定の元請けに売上の大半を依存している企業は、経営の持続性が低くなる傾向があると報告されています(出典:中小企業庁『中小企業白書』 )
このことからも、下請け依存は将来の経営安定性を大きく損なう要因になると考えられます。
顧客に選ばれるための信頼の重要性
下請けから脱却して自らの顧客を獲得するためには、単に技術力を示すだけでは不十分で、安心感や信頼感を積み重ねる工夫が欠かせません。
顧客が清掃業者を選ぶ際に重視するのは、「この人に任せて大丈夫か」という心理的な安心です。
そのために有効なのは、わかりやすい料金表の提示や、作業前後の写真による仕上がりの見える化です。
また、過去の実績やお客様の声を公開することで、初めて依頼する人の不安を和らげる効果も期待できます。
特に顔写真付きのプロフィールや、保険加入の有無を明示することは、小規模事業者であっても信頼性を高める有効な方法です。
こうした工夫により、価格競争に巻き込まれにくくなり、多少料金が高めであっても「安心してお願いできるから」と選んでもらえる可能性が高まります。
信頼は一朝一夕で築けるものではありませんが、日々の仕事や情報発信を通じて少しずつ積み重ねていくことで、下請け依存から脱却し、自分の顧客基盤を確立する第一歩となります。
業務用営業と在宅営業の違いを理解する
営業活動を行う際には、相手がどのような立場で、どのような基準で判断しているのかを理解することが欠かせません。
ハウスクリーニング業界では、法人を中心とした「業務用営業」と、個人を対象とした「在宅営業」とで、顧客が求めるポイントが大きく異なります。
この違いをきちんと押さえることで、無駄な営業を減らし、成約率を大きく高めることが可能になります。
・業務用(不動産会社や施設):作業の正確さ、スピード、報告の丁寧さが大切
・一般家庭:安心感や人柄、料金のわかりやすさが重視される
業務用営業では、不動産会社、賃貸管理会社、病院や介護施設などが顧客になります。
こうした法人は複数の物件や施設を管理しているため、単発の依頼ではなく「継続的に安心して任せられるかどうか」を重視します。
具体的には、作業の標準化、品質のばらつきの少なさ、スケジュールの遵守、作業後の報告書提出などが評価対象になります。
たとえば、不動産管理会社の場合、入居者募集のタイミングに合わせたスピーディーな清掃ができるかどうかが大きな判断材料となります。
一方で、在宅営業は一度きりの利用で終わるのではなく、リピートや口コミにつながりやすい特徴があります。
一般家庭の顧客は、清掃技術だけでなく「この人に家に入ってもらっても安心か」という心理的な信頼を重視します。
そのため、料金体系の明確さや、作業前の丁寧な説明、笑顔や身だしなみといった接客力も大きな評価基準となります。
また、在宅顧客は価格だけでなく、安心感や信頼できる対応を理由に業者を選ぶ傾向が強いことが、消費者動向調査でも示されています(出典:内閣府『消費動向調査』 )
このように、業務用と在宅では顧客が求める基準がまったく異なります。
業務用には「スピードと再現性」、在宅には「安心感と人柄」を打ち出すことで、それぞれのニーズに合った営業アプローチが可能となり、結果的に受注率の向上につながるのです。
ハウスクリーニング 下請けからの自立戦略
下請けから脱却する方法を検討する
下請けをすぐにゼロにすると、収入やスケジュールが一気に不安定になりやすいです。
現実的なのは、直請けの比率を少しずつ増やし、無理なく切り替えていく進め方です。
そのために、まずは数字で今の立ち位置を把握し、次に直請けで選ばれるための受け皿(メニュー・価格・予約導線)を整え、最後に計画的に時間配分を移していきます。
現状を数値で見える化する
- 月の総売上、変動費(移動・洗剤・消耗品など)、作業時間、移動時間を分けて集計します
- 粗利時給=(売上−変動費)÷(作業時間+移動時間)で、実質の稼ぎやすさを可視化します
-
直請けと下請けで別々に出すと、どこを伸ばすべきかがはっきりします
例(イメージ):
下請けエアコン1台4,000円、変動費1,000円、総時間2時間 → 粗利時給1,500円
直請けエアコン1台10,000円、変動費1,500円、総時間2時間 → 粗利時給4,250円
この差が積み重なるほど、直請けを増やす意味が明確になります。

粗利や経費をしっかり把握するには、会計ソフトを使うのがおすすめです。
私も最初はExcelで管理していましたが、やよいの青色申告オンライン ![]() に変えてから自動化されてかなりラクになりました。
に変えてから自動化されてかなりラクになりました。
特に請求書や見積書をワンクリックで出せるのが便利です。
直請けの受け皿を先につくる
- メニューを標準化:作業範囲、目安時間、仕上がり基準、保証内容を固定化します
- 価格は「基本料金+追加の目安」を公開し、不安をなくします
- 予約導線を用意:電話・フォーム・LINEの3本立て。どのページからもすぐ連絡できるようにします
-
連絡の即時返信テンプレを準備し、問い合わせ直後の不安を解消します

「どんな人が対応するのか」を伝えるには、ホームページが必須です。
もしまだお持ちでなければ、ジンドゥー ![]() ならテンプレートを選ぶだけで1日で完成します。プロフィールや料金表を載せるだけでも、問い合わせ率がぐっと上がります。
ならテンプレートを選ぶだけで1日で完成します。プロフィールや料金表を載せるだけでも、問い合わせ率がぐっと上がります。
段階的に配分を見直す
- まずは週(または月)の稼働の10~20%を直請けの営業・施工に充てます
- 受注が増えてきたら、下請けの受注枠を少しずつ減らします(例:四半期ごとに10~20%ずつ)
| 期間 | 直請けの目標比率 | 取り組みの主眼 |
|---|---|---|
| 1~3か月目 | 20% | メニュー整備、写真・料金公開、導線づくり |
| 4~6か月目 | 40% | 口コミ収集、紹介設計、反響の早期返信 |
| 7~9か月目 | 50~60% | 単価調整、対応エリア最適化、再訪ルール |
| 10~12か月目 | 70%以上 | 常連化の仕組み、繁忙期の枠管理 |
リスクを抑える工夫
- 生活費と事業固定費の3か月分を目安に資金クッションを準備
- 1社への依存を下げ、どの取引先も売上の3割を超えないように配慮
-
支払いサイト(期間)を把握し、入金時期のズレで資金繰りが苦しくならないようにします
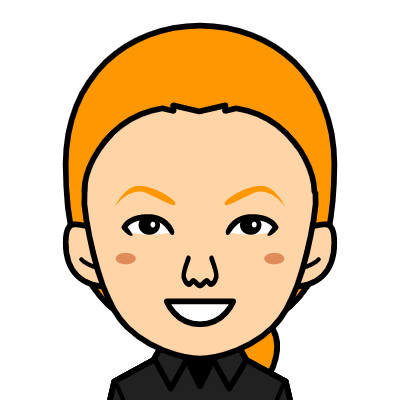
支払いサイトは、現金が入ってくるタイミングそのもんやで。条件の読み違いで資金が詰まらんように、取引前に『締め日』『検収条件』『支払日』をセットでちゃんと確認して、スケジュールと手元資金を計画的に整えていきましょ。
成果を測るかんたん指標
- 予約数/問い合わせ数(予約率)
- 直請けの平均単価・粗利時給
- リピート比率・紹介比率
-
問い合わせから初回対応までの平均時間
これらを毎月見直し、改善点を1~2個ずつ実行すると、ムリなく前進しやすくなります。
ホームページやSNSを活用した集客

直請けを増やすには、探している人に安心してもらえる情報を、わかりやすく見せることが大切です。
ホームページは「お店の顔」、SNSは「日々の様子が伝わる窓」と考え、役割を分けて整えます。
ホームページで必ず伝える5つのこと
- どんな人が対応するか(顔写真・プロフィール・保険加入)
- どんなサービスを提供するか(作業範囲・目安時間・注意点)
- いくらかかるか(基本料金と追加の目安)
- どこへ出張できるか(対応エリアと出張費の考え方)
-
どうやって申し込むか(電話・フォーム・LINEの導線と受付時間)
写真と文章のコツ
- ビフォーアフターは同じ角度・同じ明るさで撮影し、違いが一目でわかるようにします
- 作業手順は「お悩み→作業内容→仕上がり→お手入れの提案」の順で、難しい言葉を使わずに説明します
-
仕上がり保証や再訪条件をシンプルに書いて、万一の不安を取り除きます
予約と問い合わせの仕組み
- すべてのページに「今すぐ相談」ボタンを設置し、3クリック以内で予約できる形にします
- 自動返信で受付完了と目安返信時間を伝え、安心して待てるようにします
-
よくある質問(料金の考え方、作業当日の流れ、支払い方法、キャンセル規定)をまとめ、迷いを減らします
SNSは「信頼の積み重ね」を意識
- 作業の様子やビフォーアフター、道具の手入れ、安全に配慮している点など、日常の小さな工夫を短く発信します
- 週3回を目安に更新すると、見ている人の記憶に残りやすくなります
- ストーリーズや固定投稿で「当日の空き枠」「季節のおすすめメニュー」を案内すると、申し込みのきっかけが増えます
-
投稿の最後に「詳しくはプロフィールのリンクへ」と一言添え、ホームページへ自然に誘導します
この投稿をInstagramで見る

『キレイのいろは』さんのインスタは参考になりますよ。
下請けも直受けもされているみたいです。
反響を増やすミニ計画(例)
- 月初:季節の特集ページを更新(花粉対策、カビ対策など)
- 毎週:ビフォーアフター2件、よくある質問の回答1件を投稿
-
月末:お客様の声を1件追加し、トップページに掲載
振り返りと改善
- ホームページのアクセス数、問い合わせ数、予約率を毎月チェックします
- 「よく読まれているページ」と「予約につながったページ」を見て、写真や文章、ボタンの位置を少しずつ直します
-
電話とフォーム、LINEのどれが一番使われているかを比べ、案内の順番を入れ替えて試します

このように、伝える内容を整理し、見つけてもらいやすい導線を整え、少しずつ改善を重ねていくことで、直請けの受注が着実に増えていきます。
名刺やチラシで安心感を与える工夫
地域で直請けを増やすには、名刺とチラシはまだまだ強力な武器です。
特に、年配の方やネットが得意でない方にとっては、紙の情報のほうが安心感があることも多いです。
名刺に必ず入れておきたい情報
- 屋号・氏名・顔写真
- 連絡先(電話・メール・LINEなど)
- 主なサービス内容と料金の目安
- 対応エリア
- 損害賠償保険加入の有無
- ホームページやSNSへのQRコード
名刺は「最初に手に取ってもらうミニホームページ」のようなものです。
顔写真や簡単なプロフィールがあるだけで、初対面の緊張がかなり和らぎます。
受け取った側も、「この人だったらお願いしても大丈夫そうだな」とイメージしやすくなります。

名刺づくりの具体的な流れや、ネット印刷でラクに作る方法は、ハウスクリーニング営業用の名刺をラクスルで作った体験談で詳しく紹介しています。デザイン例も載せているので、1枚目の名刺づくりの参考になると思います。
チラシは「安心」と「強み」を両立させる
チラシを作るときにやりがちなのが、価格だけを大きく打ち出してしまうことです。
もちろん価格も大事ですが、それだけだとどうしても値下げ競争に巻き込まれやすくなります。
チラシに入れておきたい要素は、次の通りです。
- 顔写真付きのあいさつ文(どんな思いで仕事をしているか)
- 人気メニューと料金の目安
- ビフォーアフター写真
- お客様の声(イニシャル・年代など)
- 対応エリアと連絡先
この5つがバランスよく載っていると、「誰が・どんなサービスを・どこで・いくらくらいでやってくれるのか」が一目で分かります。
ここが分かるだけで、お客様の心理的ハードルはかなり下がります。
チラシづくりの参考

私はチラシを作るとき、パワーポイントで自作したものを印刷会社に入稿しました。具体的なレイアウト例や作り方は、ハウスクリーニングのチラシをパワーポイントで作る方法で実物のイメージと一緒に解説しています。デザインに自信がなくても、型を真似るところから始めれば十分ですよ。
差別化につながる専門サービスの提案
独立して営業をしていく中で大切なのは、「よそと同じことをしていては結局値段勝負になる」ということです。
だからこそ、自分のお店はここが強みなんです! とハッキリ伝えられるようにすること、つまり差別化が必要になってきます。
たとえば、不動産屋さんに空室清掃の営業に行ったとします。
不動産屋さんは日ごろから多くの業者さんの営業を受けていますので、「ただの掃除屋です」ではなかなか響きません。
そんなときに「不動産管理専門の清掃業です」とか「空室を埋めるための清掃サポートをしています」と名乗るだけで、相手の印象は大きく変わります。
専門性を打ち出すことで「この会社は他と違うな」と思ってもらえるのです。
さらに、その専門性を裏づける工夫も必要です。
たとえば、空室清掃のあとにオゾン脱臭機で臭いを取るサービスや、掃除中に気になったところをチェックシートにまとめて報告するサービス、入居が決まった後に簡易的な再クリーニングを安価で行うサービスなど。
「ここまでやってくれるなら安心だな」と思ってもらえるポイントを準備しておくと、仕事が決まる確率はぐっと高まります。

実際に私自身も、配管の高圧洗浄をお願いするときに「高圧洗浄専門」とうたっている業者さんに依頼しました。
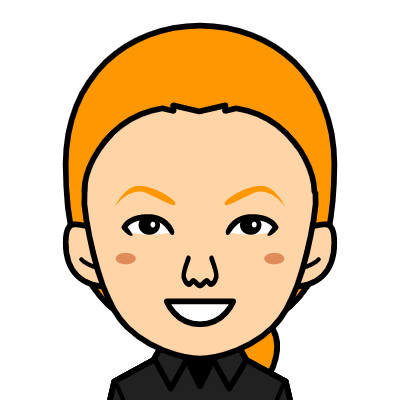
たしかに“専門”って聞くと、ちゃんとやってくれそうやし、安心感するよね。
一方で、一般家庭向けの営業はまた少し違います。
新規のお客様に知ってもらうためには、チラシのポスティングが効果的ですが、ただ価格を書いただけのチラシではなかなか反応はありません。
大事なのは、安心感を与えることです。
例えばAmazonで買い物をするとき、レビューを確認して「評価が高いなら安心」と思うのと同じように、お客様も「この人に頼んで大丈夫かな」と不安に感じています。
その不安を解消するために、チラシにはお客様の声や写真、自分自身の顔写真やプロフィールを載せると効果的です。
「どんな人が来るのか分かる」だけで安心感が増し、問い合わせにつながりやすくなります。
つまり、業務用でも家庭用でも共通して言えるのは「他のお店と違うところをアピールすること」です。
専門性を打ち出したり、安心感を伝えたりすることで、値段を下げなくても選ばれる理由を作ることができるのです。
協力会社との連携で広がる可能性
独立当初は、自分の仕事と下請けの仕事が半々という形でスタートする方も多いと思います。
私自身もそのような状況から始まりましたが、地道な努力を重ねた結果、約2年後には自分の仕事だけで100%を構成できるようになりました。
現在、下請け中心の仕事で苦労されている方も、あきらめずに少しずつ「自分の仕事」を増やしていくことが大切です。
具体的には、業務用と一般家庭の両方に向けた営業活動を行うことで、着実に自社案件の比率を高めていくことが可能です。
さらに、他の業者さんと積極的に繋がり、信頼関係を築くことも欠かせません。
私の場合は、電気工事業者、リフォーム業者、不動産会社、ふすま屋さんなど、幅広い分野の方々と交流しています。
ポイントは、まずこちらから「ギブ」をすることです。
こちらが先に協力し、相手にメリットを提供することで、やがては紹介や新しい案件を回していただけるようになります。
その際、重要なのは「win-winの関係」であること。もし相手が自分の利益しか考えない「テイカー」であれば、無理に付き合い続けず、誠実な協力関係を築ける業者さんを探した方が長期的には得策です。

このように、地道に営業活動を続け、信頼できる仲間を増やしていけば、私のように下請け中心から脱却し、自分の仕事100%の体制を築くことは十分に可能です。
まとめとしてのハウスクリーニング 下請け脱却の結論
この記事をまとめます。
-
下請けは仕事は安定するが儲けが少ない
-
元請けに依存すると自由がなく不安定になる
-
直請けは自分の顧客を持てて紹介が増える
-
信頼を作る工夫が直請け成功のカギになる
-
作業前後の写真や保証が安心感を与える
-
料金やサービス内容をわかりやすく示す
-
業務用と家庭用で営業方法を変える必要がある
-
ホームページは必ず料金と事例を載せる
-
SNSで日常の作業を発信すると親近感が出る
-
名刺やチラシは顔写真入りで信頼を高める
-
お客様の声を載せると新規も安心できる
-
他社と差をつける工夫で価格競争を避けられる
-
協力会社とつながると仕事の幅が広がる
-
小さな直請けを積み重ねて割合を増やす
-
焦らず少しずつ下請けから抜け出すことが大切
\実際に現場で使っているハウスクリーニングおすすめ洗剤&道具/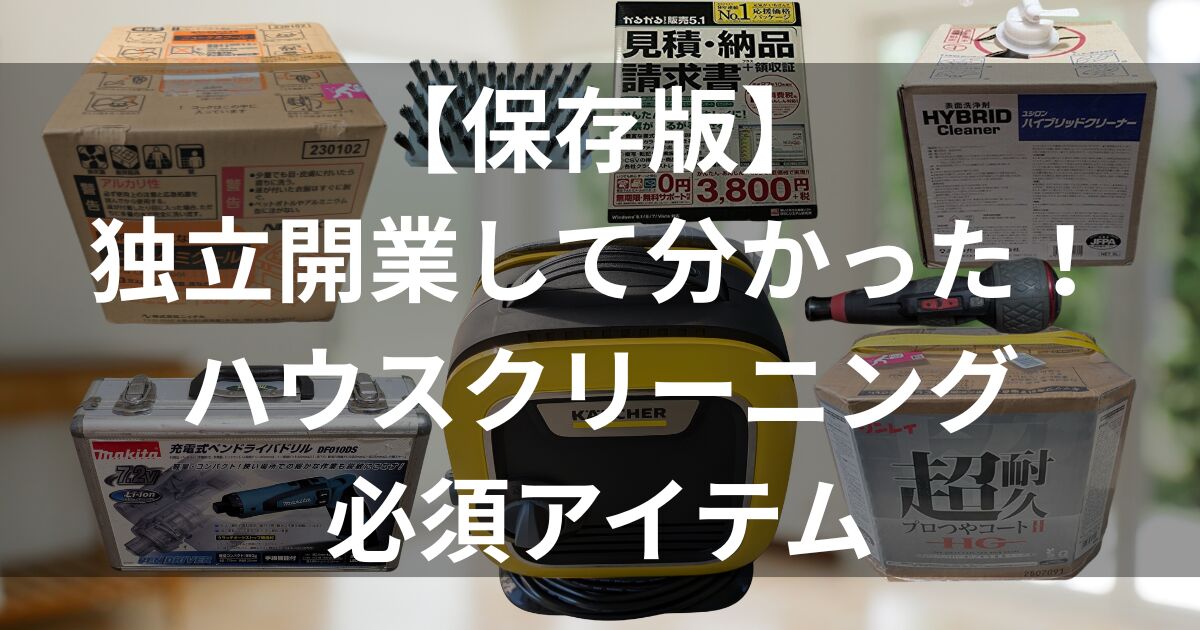
独立開業を目指すとき、最初に悩むのが「どんな洗剤や道具を揃えればいいのか」「経理や顧客管理はどうするのか」、そして「一人で不安になったときに頼れる場所があるのか」という点ではないでしょうか。
私自身、開業当初は同じように迷い、必要のないものを買ってしまったり、逆に本当に必要な道具が抜けていて現場で困った経験があります。
また、事務作業に追われて時間を失ったり、孤独感に押しつぶされそうになったこともありました。
そうした失敗や試行錯誤を経て、「これだけは導入してよかった」と胸を張っておすすめできるものがいくつかあります。
それが 『洗剤・道具・会計ソフト・コミュニティ 』の4つです。
これらを揃えることで、作業効率が大きく向上し、顧客からの信頼も得られ、さらには安心して長く続けられる基盤が整いました。

私が現場で実際に使って「これは間違いなく役に立つ」と感じたものだけをまとめました。これから独立開業される方の参考になると思いますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
👉 『【保存版】独立開業して分かった!ハウスクリーニング必須アイテム』を詳しく見る
【この記事を書いた人】

清掃業歴20年以上、累計1万件以上の現場を経験。
大手清掃会社に14年間勤務し、現場管理やスタッフ育成、顧客対応を通じて豊富なノウハウを習得。
42歳で独立後は、住宅・オフィス・店舗清掃を中心に活動中。
このブログでは、清掃業での独立ノウハウ、集客術、現場トラブル解決法などを実体験に基づいて発信しています。